この記事では、クライミング上達の核心とも言える【保持力について】を説明しています。
強いといわれるクライマーたちは「保持力」が一般人のそれと違います。
保持力は簡単に言うと”持つ力”のことを指し、クライミングの基礎力であり、最も重要な能力といえます。
保持力を鍛えていくことは、グレードを上げていく上でも大変重要ですよね。
クライミング10年以上の経験、7年間ジムスタッフとしての経験、四段を登れたという経験、クライミングの本やブログを読み漁った経験を参考に執筆しました。

保持力ってどうやって鍛えるの?



保持力弱い…



そもそも保持力ってなに?
このような悩みや疑問を抱えている方は特に読み進めてみて下さいね。
この記事では「保持力」について以下の順番で紹介しています。
- 保持力の定義
- 保持力向上方法3つ
- 保持力を瞬間的に上げる方法
この記事を読んでいただき、あなたの努力による保持力向上の結果、「より楽しいクライミング」「目標の達成」の手助けができれば幸いです。
この記事を書いた人
ぶちょー(クライミング飛鳥店長)
15歳からクライミングをはじめ、現在30歳。
趣味は読書やカメラ。
【登ってきた主な課題】
最高RP 四段+(V13) 5.13d
ハイドラ(四段+) フルチャージ(四段) Ammagamma (V13)Midnight Lightning(V8)などなど
リキッドフィンガー 5.13d


\意外と楽しい!世界で流行りのボルダーボール!/
そもそも保持力って?
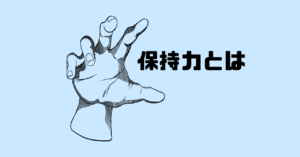
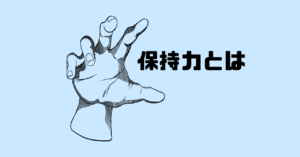
「保持力」とは、簡単に言ってしまえば”ホールドを持つ力”になります。
保持力が無いと、ホールドは持てずに指が開いてきてしまいます。
保持力があれば、ホールドを離さずに次のムーブに移行できますね。
そんな「保持力」と呼ばれているものに対して、クライマーによって様々な定義をしています。
- 指が開かない強さ
- ホールドを離さずに次のムーブに移行できること
- 親指を除いた4本の指が支えられる最大重量
- どれだけ小さいホールドが長い時間もてるか
- どれだけ小さいホールドがもてるか
- どれだけ多くのホールドがもてるか
等々、多くの意見があり、中には”単純に腱の強さ”を保持力と定義している方もいます。
僕が思う保持力は”ホールドを離さずに動ける強さ”が「保持力」だと思っています。
持てても動けなければ意味無いですから。
持って動ける。これぞ保持力。(個人的意見)
最近、日本語訳され発売された著書「BEASTMAKING」にはこうあります。
「指の力」があるほど、より悪いホールドが持て、ムーブも起こせる可能性が高まる
BEAST MAKING p44 ”「指の力」とは何か”より引用
保持力の向上させ、様々なホールドを持てるようにするためには、大きく分けて3種類の方法があります。
- コツコツ強化していく
- 上手くなる
- 軽くなる
以上の3つで保持力が向上します。
これらは、多くの努力や経験が必要で、すぐに保持力が向上するものではありませんので注意してください。
さらに、初級者の場合、「保持力トレーニングよりもクライミングの動きの習得や、体の連動性を高めるトレーニングをした方が上達する」ということを覚えておいてください。
\今、あなたがやるべきトレーニングを見つけたい方はこの記事がおすすめ!/
保持力を向上させる方法①指をコツコツ強化していく
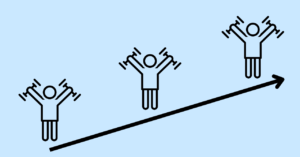
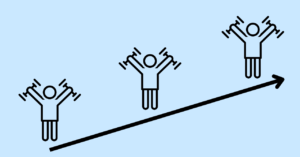
本来、ホールドを離さずに持っていられる力、すなわち”指の腱や筋肉”というのは一朝一夕で強化されるものではありません。
数年という歳月をかけて、少しずつ強くなっていくものなのです。
腱を強くするには、毎回のトレーニングで腱や筋肉に負荷を与えることで少しずつ強靭なものとなります。
適当に登っていては、何年たっても保持力はつきません。
では、保持力を鍛えるにはどうしたらいいのか説明します。
以下の項目を考えていきましょう。
- 回復が保持力upの鍵
- 腱の強化は可能か
- 力の出し方
- 多角度から保持力を攻める
- キャンパシングとフィンガートレーニング
\この記事も参考にしてみて下さい!/
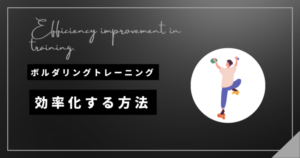
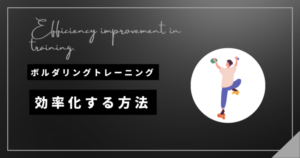
回復力が保持力アップにつながる
トレーニングを行った後、負荷をかけた部位を回復させないと体を壊してしまいます。
保持力トレーニングを高負荷で続けることはパキリにつながり、重度の場合は2ヵ月以上クライミングができなくなります。
これを防ぐためには「休養」と「栄養」をとることが必要です。
負荷がかかった筋肉にはプロテインやEAAなどのアミノ酸がオススメです。
腱は強化ができる
指の腱の強さは保持力に直結します。
保持力が弱いと腱に高負荷の力が加わり、炎症や損傷を起こすと「パキる」のです。
その高負荷に耐えられる腱の強さを手に入れるにはどうしたらよいのでしょうか。
文献によると「エキセントリックトレーニングが腱の回復に有効」ということがわかります。
エキセントリックトレーニングとは力を入れていく動作ではなく、力を抜いていく動作のトレーニングを指します。
懸垂で例えると、上がる動作ではなく下がる動作で腱は強くなることになります。
指で例えると、握り込む力ではなく、指が開いていく時に力を入れることで腱が強くなっていきます。
- Increased mRNAs for procollagens and key regulating enzymes in rat skeletal muscle following downhill running
- Eccentric training improves tendon biomechanical properties: a rat model
- Eccentric rehabilitation exercise increases peritendinous type I collagen synthesis in humans with Achilles tendinosis
101の力を出す保持力トレーニング
もし、あなたが100の保持力を持っていたら、101の保持力を出せば強くなります。
この101は102にする必要はありません。
101の力が出ていれば十分強くなるのです。
これはトレーニングの原則であると同時に、クライミングはウェイトトレーニングと違い、自分の限界の数字が見ることができないので難しい問題です。
トレーニングが下手な人は、保持力のための筋や腱にうまく刺激が与えられなかったり、心理的な限界が低いと101に到達できません。
他には、自分の限界がわからず限界以上の力を出してしまったり、ダラダラと力を出し続ける、トレーニング終盤に101を出そうとする、などして限界を超えすぎると故障、怪我、パキりにつながります。
(パキりとは・・・指や掌、前腕などの筋肉や腱を痛めること。腱などに強い負荷がかかった時、損傷した瞬間にパキっという音がなることがあるため「パキる」という。実は音がならないほうが多い。)
限界まで追い込めたのかが分かる指標として、トレーニング後、軽い筋肉痛になるということが101の力が出せている証拠となります。
軽い筋肉痛で十分です。
ハードなトレーニングをして、何日も筋肉痛。
これはただの自己満足であり、効率的なトレーニングではありません。
筋肉痛がひどい時、相乗して筋肉が増えるわけではないのです。
毎回のトレーニングで101を出す。
これを続けましょう。
逆に言えば101を出せればその部位は強くなるため、何時間も登る必要はありません。
ただし、体の連動やムーブ、脱力のトレーニングは短時間では鍛えることができません。
注意することとして、全力を出すトレーニングは体が温まっていない時に行うと危険ですので、ウォーミングアップは必ず行ってください。
保持力はひとつじゃない


保持力とは前述の通り
”腱の強さ”であり、
”多くのホールドが持てる強さ”であり、
”ホールドを保持しながら動ける強さ”なのです。
このことからも、保持力を鍛えることは単純な話では無いことが分かります。
ここで、僕が言いたいのは「極小カチの保持力」と「ピンチの保持力」、「スローパーの保持力」は少しずつ違ったものである。
ということに加え、「ホールドの向き」「ホールドの遠さ」など、課題によって違うのではないか。
ということです。
自分が欲しいと思う保持力をつけるにはトレーニングの種類(持つホールドの種類)を変化させていかなければいけません。
ピンチを持つときの筋肉は、カチを持つときに使う筋肉と少し違うのは想像しやすいと思います。
しかし、カチの持ち方によって使う筋肉が微妙に違ったものになることは知っていますか?
カチの持ち方は3種類。
フルクリンプ(アーケ、カチ持ち)
ハーフクリンプ(セミアーケ)
オープン(タンデュ、オープンハンド)
それぞれ微妙に使う筋肉の場所が違うのです。
詳しく書くと長くなるので、また別の記事にて。
他には、使う筋肉の種類ではなく使い方の話になります。
長時間保持する持久力的(ストレニュアス)な保持力なのか、一瞬で保持する保持力(コンタクトストレングス)なのか。
これも鍛え方が違いますね。
要は、持ち方や動き方でそれぞれ使う筋肉や使い方は違うため、見極め、考えながらトレーニングしなければいけないのです。
ここまで読み進めてくれた方にはわかると思いますが、保持力トレーニングっていうのはとても難しいのです。
漠然と「保持力が欲しい」と願っているならば、たくさん課題を登り、いろいろな種類のホールドを持ち、満遍なく鍛えていくことで保持力の強化に繋がります。
鍛える部位を「意識する」ことは大切で、意識することにより効果的に鍛えることができます。
逆に、漠然とではなく「この課題が登りたい」などの目標がある場合、その目標の課題を打ち込むか、その課題に似た動きや保持感を再現してトレーニングをします。
それを繰り返しましょう。
そうすれば結果的に自分にとって弱い保持力は強化されるでしょうし、「どこどこを鍛えなければいけない」を考えずに済みますよね。
気を付けなければいけないことは、苦手だと思う課題も目標にしてトレーニングしなければなりません。
偏ってしまいますから。
キャンパシングとフィンガーボード
保持力強化と聞いて、キャンパシングやフィンガーボードを思い浮かべた方は少なくないと思います。
キャンパシングは一瞬で保持する能力(コンタクトストレングス)や体幹、各部位の筋動員率を向上させるためのトレーニングです。


こちらは”動くため”のトレーニングです。
反対に、フィンガーボードは悪いホールドを持って耐える持久力向上と、より悪いホールドを持つための限界トレーニングとなります。
ビーストメーカーは”持つため”のトレーニングです。
どちらも保持力トレーニングとしては負荷が高く、中級~上級者向けのトレーニングだと認識しておきましょう。
筋肉が十分についていて、トレーニング基礎がわかっている方のみ推奨されます。


保持力を向上させる方法②上手くなる


前項の”保持力向上法①”で説明したのは「指を鍛えて保持力を鍛えよう」というもの。
その②では指以外に焦点をあてます。
僕がこの記事で伝えたいことの8割はこれ。
- いなす
- 繰り返す
- 神経活動量を増やす
残り2割は一番最後に書いてあります。
「保持力を強化」したいなら、コツコツ鍛えるのと同時に”クライミングが上手くなりましょう”。
保持力が強い人は、持って動けます。
そう、持てるだけではダメなのです。
ここで述べた「動き」とはムーブであったり、体の位置、体幹の使い方、下半身でいなすことを指します。
上手い人は保持感(ホールドを保持している感覚)が一番良いところに体を動かせるため、無駄な力を使いません。
力の強さや出力時間も最低限抑えることができます。
さらに、ホールドを見極め、より保持しやすい位置を瞬時に見つけます。
保持力は腕の筋肉や腱の強さだけではありません。
「足りない保持力を補える力」もまた、”保持力”なのです。
脱力する、壁に近づく、足や腰の力を使う、ムーブを洗練させる、最も持ちやすいところを持つ、指の使い方を改善、保持する時間を減らす、などなど。
これらがカチッとハマれば保持力は向上します。
クライミングが上手くなるには確実に経験が必要で、経験とは今までに集中して登った量です。
たくさん登りましょう。
上手い人を真似ましょう。
そして、悪いホールドに対応できる動きを身につけて下さい。
悪すぎるホールドは指の力以外でいなさないといけないのです。
力の出力の大きさ(筋力)は筋肉量だけでは決まりません。
なぜなら、筋肉量に加えて「神経活動量」と「心理的要因」が筋力に影響するからです。
よって、筋肉量を上げて保持力を向上させるというのは、保持力の3分の1しか強くならないのです。
小山田大さんはこんな感じに仰っております。
いなすっていうのは、これは自分でも上手く説明できないんですが、全身のコーディネーションというのかな。足をうまくさばいて、そのさばき方でホールドを保持していくということです。
出典:rock&snow082 小山田大インタビュー




保持力を向上させる方法③軽くなる


保持力向上方法その3、「軽くなりましょう」
クライミングは重力に逆らい自重を押し上げていきますよね。
この記事に沿っていえば、「保持力を使って自分の体を持ち上げていく」のです。
自分の体が重ければ、余分な保持力を使います。
はい。
なので、軽くなりましょう。
軽くなれば、余分な保持力使いませんから。
さて、軽くなるにはどうしたらいいのか。
自分の体についている”無駄な重り”を排除していきます。
脂肪、筋肉などなど。
まず、思いつくのは脂肪ですね。
食事管理を徹底すれば、クライマーならすぐに落とせるはずです。
ストイックな人多いですから。


脂肪より重く、厄介なのが筋肉です。
体質にもよりますが、筋肉がつきやすい人は特に注意が必要となります。
登れないからといって、安易にハードな筋トレをしていませんか?
筋肉はうまく使えていなければただの重り。
”より楽に登れる技術”が身につく前に力で無理やり登ってしまうようになると、手数の多い課題が対処できなくなったり、神経系のトレーニングも難しくなってしまいます。
筋トレよりも先にやらなければならないことは、うまく筋肉を使えるようになることです。
難しい課題をやっていれば、おのずと必要な筋肉はついていきます。
筋肉も脂肪も、食事を減らすことでどちらも減少しますが、無理なダイエットは体を壊すことになるので栄養管理は綿密に。
おやつを控える、アルコールを控えるなど、できることからやっていきましょう。
軽くなるためにできることとして、「登る前の暴飲暴食を控える」「トイレに行く」「無駄な服は脱ぐ」「腰のチョークバックを外す」など、その場でできることもありますね。
パーカーや厚手の服はクライマー向きではありません。
(モラルに欠けない範囲で)1gでも軽くしましょう。
瞬間的に保持力を向上させる方法


保持しにくいホールドを持った後、それよりも保持がしやすいホールドを持つと、普段よりも持ち感がよくなる現象を感じたことがりますか?
自分の限界値を精神的に押し上げているからでしょうか。
これは、メンタルで保持力が向上する…よな…
という域をでないため、本題では述べませんでしたが、実際に僕は感じています。
「あの時はこれ以上悪いホールドを持っていた」
「あのホールドは持てる」
という精神的な余裕が、最大の力を出すためには必要なのかもしれません。
保持力は「メンタルが強くなることでも向上する」と僕は思います。
「恐怖」や「未知」は力を制限しますから。
逆に、「ワクワク」していたり「喜んでいる」と力が出るのです。
これ、大切です。
一度、悪いホールドを持った後に、少し悪いホールドを持つと普通よりも楽に持てたと感じる現象は神経系が活性化されることによるもので
「PAP (Post-Activation Potentiation:活動後増強)」
というようです。





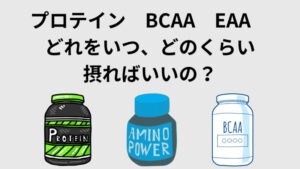




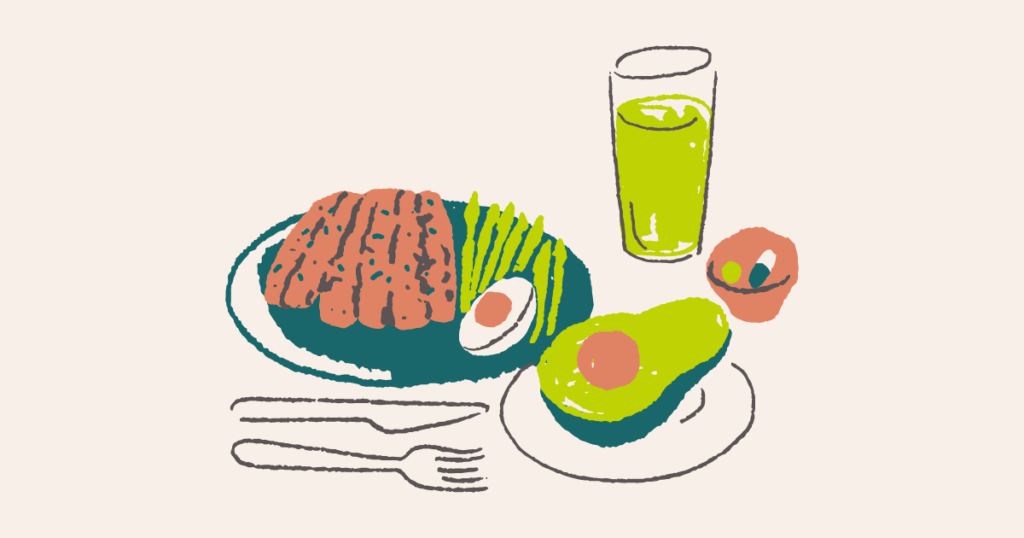




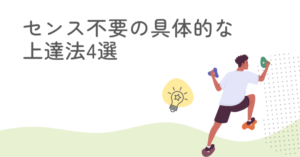
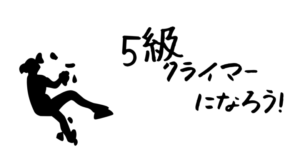

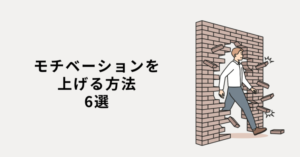



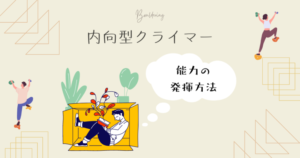
コメント
コメント一覧 (2件)
[…] 【保持力弱い】クライミングの保持力を鍛える方法3選 […]
[…] 【保持力弱い】クライミングの保持力を鍛える方法3選 […]