世間には静かな人、おとなしい人と呼ばれる、内向的な人がいます。
内向的な人は能力があるにもかかわらず、それを見せたり表現するのが苦手なため、不当な評価をもらうことはめずらしくありません。
さらに本来は内向的なのにもかかわらず、外向的な性格を求められて疲弊してしまう方もいます。
そんな”内向型”と呼ばれる人たちは、能力の使い方次第で素晴らしい結果を出すことができます。
内向的なクライマーが、いかにボルダリングに向いているのか説明します。
内向型クライマーの奥底で密かに燃える炎は他人には見えにくいですが、大きく強く揺らいでいるのです。
この記事では、以下を詳しく説明していきます。
- 内向型と外向型の違い
- 内向型クライマーの強み
- メリットとデメリット
- 外向的になる唯一の方法
- 内向型クライマーのトレーニング
この記事を執筆する理由は、「一人で黙々と登っていて強くなるのかな?」という疑問が、ずっと僕の心のどこかにあったからです。
何を隠そう、僕も内向型クライマーの1人です。
コンペやセッションで活躍し強くて輝いている人を見ていると、自分のトレーニングの方向が間違っているのではないか、という不安がありました。
僕は人の少ないエリアに好んで行きます。
知らない人たちのセッションは混ざれないし、コンペなどもってのほかでした。
今はある程度経験も積み、多少ですが登れるようになったため、昔より一人で登る時間は減りました。
それでもまだ人の多いところやコンペは苦手意識が強く、自分の意見を言葉にするのもうまくありません。
(接客業従事者としてどうなんだ…)
しかし、無理に自分を外向的に変えようとすると疲れてしまいます。
そこで、内向的な性格の強みを学び、まとめてみました。
結果的に、僕のこの「言葉ではなく文章にする」ことも内向的な性格の強みの一部だったようです。
自分が内向的な人間だと感じている方が、強みを活かしたトレーニングを見つけ、ストレスのないボルダリングをしてほしいと思い、この記事を執筆しています。
この記事を書いた人
ぶちょー(クライミング飛鳥店長)
15歳からクライミングをはじめ、現在30歳。
趣味は読書やカメラ。
【登ってきた主な課題】
最高RP 四段+(V13) 5.13d
ハイドラ(四段+) フルチャージ(四段) Ammagamma (V13)Midnight Lightning(V8)などなど
リキッドフィンガー 5.13d

前置きが長くなってしまいましたが、内向的な人と外向的な人の違いを説明していきます。
内向型、外向型

はじめに、自分の性格を最も正確に測定できる性格診断のリンクを貼っておきます。
もし、自分が内向的なのか、外向的なのか分からない場合は測ってみて下さい。
すべて回答するのに10分ほどかかります。
ちなみに僕の内向性は82%…
(信頼性はS判定)

内向型と外向型の違い
まず、内向型の人と外向型の人の違いを簡単に説明します。
内向的な性格は静かで内省的で、一人でいる時間を好みます。
一方、外向的な性格は社交的でコミュニケーションを楽しみ、他者とのつながりを大切にするといった違いがあります。
ちなみに人口の3分の1は内向的な性格と言われています。
※アメリカの統計で日本にはもっと多くいる。さらにそこからクライマーに絞ると割合が増えると思われる。
性格は生まれつきなのか
次に、性格の形成について説明します。
性格には生まれつきの要素(先天的な側面)と環境や経験によって形成される要素(後天的な側面)があります。
そして、誰でも内向的な性格と外向的な性格の両方の側面を持っていますが、どちらがより顕著に現れるかは個人によって異なります。
つまり、僕たちは皆どちらの性格も持っていることになります。
人は内向型や外向型に完全に分類されるわけではなく、その瞬間によって表れる性格は変化します。
たとえば、ある時は内向的な特質が目立ち、別の時には外向的な特質が強く出るというように、状況によって変わるのです。
性格を理解することが大切
ボルダリングにおいて、「自分は内向的だから」といった決めつけによって、コミュニケーションを避ける選択は悪手です。
ボルダリングでの成長や上達にはコミュニケーションも重要であり、コミュニケーション不足はケガや事故を引き起こす可能性もあります。
自分の性格特性を理解することは非常に重要です。
なぜなら自分の性格を理解することで、疲労軽減、自己成長、他者との良好な関係作りに役立てることができるからです。
さて、そこで内向的なクライマーの特性を理解するために、次の項目では内向型クライマーの強みを紹介していきます。
内向型クライマーの強み~一人で黙々と登る人~

黙々と登るのが好きな人は共感力が高い
セッションなどでガヤガヤと楽しそうに登っている人達、いわゆる「外向的な人達」の傍らで、ひたすら黙々と登っているクライマーがいます。
楽しそうなセッションの影にひっそりと隠れてしまうような静かなクライマーは、一見すると
「楽しいのかな?」
「寂しくないのかな?」
なんて思われてしまうかもしれません。
しかし、本人たちは自分と向き合う時間や一人で考えている時間を大切にし、それをクライミングの楽しさだと感じているのです。
今どきの人はそれを「コミュ障」、「陰キャ」なんて言葉を使いますが、それは違います。
内向的な人は、高い共感力のせいで外側からの刺激にとても敏感なだけであり、必要以上に多くの情報を得てしまうため疲れてしまうのです。
高すぎる共感力を持つとHSP(Highly Sensitive Person)と呼ばれ、人口の5人に1人が当てはまると言われています。
世間は「コミュ障」「陰キャ」なんて言葉を作り、内向的な人達の価値観を否定しますが、内向的な人にも誇れる能力があります。
例えば、”深い川は静かに流れる”という言葉があるように、内向的なクライマーは自分の内側に意識を向けて深く考えることが得意です。
さらに、内向的な人は外向的な人に比べて観察能力が高く、自制心が強く、粘り強いといった特性を持つことがあります。
反対に、外向的な人達は刺激に鈍感で、自分をアピールする能力が高く、リスクを恐れにくいといった特性を持っています。
内向的な人の能力は表面には表れにくく、他者から理解してもらえないことがあります。
そのような内向的な人たちは、自分をアピールすることができる外向的な人達に埋もれてしまいがちです。
さらに、世間は外向的な人を理想とする価値観の中で暮らしています。
それは、アニメや漫画で活躍する主人公たちが軒並み外向的な性格であることから見て取れます。
話の上手い人はそうでない人より賢く、会話の多い人はそうでない人よりも有能と評価されています。
このような背景から、内向的な人の能力が不当な評価をされていることが少なくありません。
内向型クライマーの強み
内向型クライマーに現れる強みを紹介します。
(前項でも触れた通り、人それぞれに程度があり、内向的な人にすべてが当てはまるわけではない)
- 深い思考が得意
- 観察能力が高い
- 自制心が高い
- 分析能力が高い
- 客観視ができる
- 粘り強い
- 用心深い
- 一人でもパフォーマンスが低下しない
- 仲間のつながりが深い
- 本質を見る
この強みを活かし続けると、「オンサイト能力」「ムーブの精度」「練習密度」が向上することが考えられます。
要するに内向型のクライマーは技術が磨かれやすいということです。
内向型のメリットとデメリット
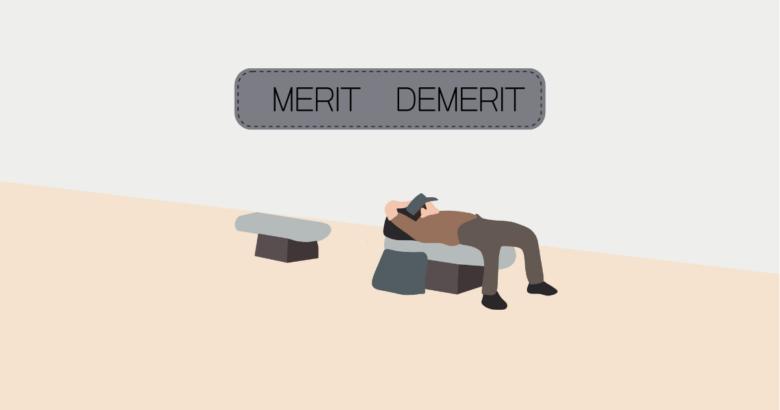
強みを紹介してきましたが、もちろん内向的なクライマーのデメリットもあります。
| メリット | 説明 |
|---|---|
| 深い思考力 | 内向的な人は自己反省を重視し、深く考える傾向があるため、洞察力が高く、問題解決能力に優れる。 |
| 集中力が高い | 静かな環境で集中できるため、アートや専門的な作業に向いている場合がある。 |
| 内面的な豊かさ | 内向的な人は内省が得意なため、感情や想像力が豊かな傾向がある。 |
| 信頼性がある | 内向的な人は言動が慎重であるため、他人からの信頼を得やすい。 |
| デメリット | 説明 |
|---|---|
| 社交的な機会への適応が難しい | 外向的な環境や社交的な場に適応するのが難しいため、新しい人間関係を築くのに時間がかかることがある。 |
| コミュニケーションの壁 | コミュニケーションにおいて、自己主張が弱く、自分の意見を上手に伝えることが苦手なことがある。 |
| 孤独感 | 長時間の孤独を好む傾向があり、社交的な場での孤立感を感じることがある。 |
| 緊張しやすい | 緊張しやすく、過度に内向的な場合は、新しいチャンスを逃すことや自己成長を妨げることがある。 |
まとめると、内向的な人はチームスポーツには向いていないということがわかります。
反対に、内向的な人は個人競技であるボルダリングに向いているし、ハマりやすいのではないでしょうか。
クライマーとしてのデメリットは以下の通りです。
- コンペなど注目が苦手
- 人の多いところが苦手
- セッションが苦手
- 競争機会を逃す
- その場で処理が苦手
- 遠征の機会を逃す
- 孤立感
人が多いほどパフォーマンスが低下する内向型クライマーですが、一瞬だけ外向的な側面を呼び起こすことができます。
その方法を次項で説明します。
内向的なクライマーが外向的になるには

基本的にクライミングは一人で登るトレーニングが多いですが、ジムに通っていると「セッション」が開催されることも多いと思います。
気心が知れた仲間うちならともかく、知らない人とのセッションは内向型のクライマーにとってはストレスに。
その場では楽しそうに振舞えても、家に帰ったらどっと疲れることがあるのです。
そのような時は内向的な人が「自由特性理論」を使うと外向的に振舞えるのです。
自由特性理論
ハーバード大学のブライアンリトル教授が提唱している【自由特性理論】とは、「コア・パーソナル・プロジェクトに従事するときは特性の枠を超えて振る舞うことができる」というものです。
これは要するに、好きなことをしている時や大事だと感じること、大切な人には外向性を発揮できるということです。
例えば、長い付き合いの友人と一緒に登っている時や、成長できる機会が訪れた時に外向的に振舞うことができるようになるのです。
ただ注意点として、没頭できたり、ゾーンに入れることをしている時のみ効果を発揮します。
このことから、自分の成長につながるというマインドを持てば、セッションなどにも参加しやすくなるのではないでしょうか。
ちなみに、内向型の人でも「セルフモニタリングができるひと」は上手く外向的にふるまえます。
それは、自分の言動や感情を観察し、状況に応じて行動をコントロールできる人を指します。
このように状況に順応し、外向的にふるまうのが得意な内向的な人もいます。

友人をまずは1人作る
内向的なクライマーにとって、新しいコミュニティに移動した時が最もストレスを感じます。
遠征のジムでは一時的なので気にしなくてもよいでしょうが、転勤や引っ越しによってホームジムが変わった場合、一人での黙々と登る時間が続きがちです。
黙々と登るだけで満足できるような内向型クライマーでも、強くなるためにはセッションも必要です。
なぜなら自己認識を超えた発見が可能となり、メンタルブロックを崩しやすいからです。
そこで、内向型クライマーへのおすすめの方法は、まずは一人と仲良くなることです。
一人と仲良くなったら少しづつコミュニティを広げてみてください。
ある程度そのジムに慣れても、トレーニングは少人数の気心しれた仲間うちで行いましょう。
決して見知らぬ集団に飛び込んではいけません。
ドーパミンをハックする
ドーパミンの量が増えれば増えるほど前向きとなり、外向的なるということがわかっています。
ドーパミンを増やす方法は以下の通りです。
- 運動
- 適切な食事
- 良い睡眠
- ストレス管理
- 新しい挑戦
- ソーシャルなつながり
- 自己報酬
一人で黙々と登る人たちのトレーニング
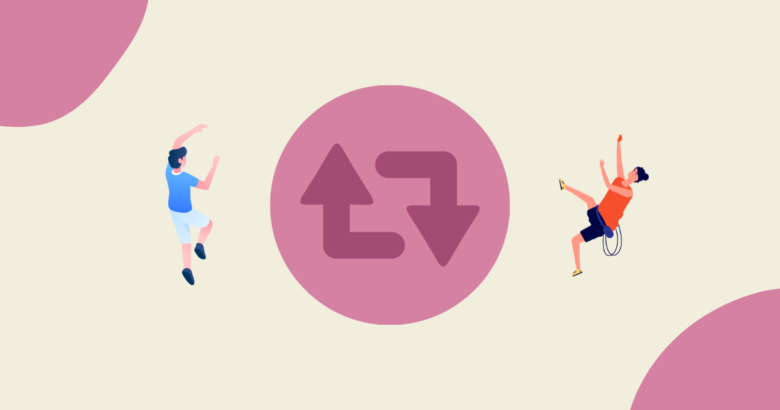
さて、ここまで内向型クライマーの強みと外向的になる方法をお伝えしてきました。
この項目では、内向的なクライマーにおすすめのトレーニングを紹介します。
結論から言うと、内向型クライマーには「サーキットトレーニング」がおすすめです。
一人で黙々と登るトレーニングの代表格「サーキットトレーニング」は次々と登るトレーニングになるため、他者と話すタイミングがほとんどないからです。
そもそも、ボルダリングというスポーツ自体、内向的な人が輝けるスポーツです。
それは、個人競技だからということもありますが、一番は「自己成長の嬉しさを最も感じることができる」点にあるのではないでしょうか。
例えば、「できなかった課題ができるようになる」「できなかった動きができるようになる」これらの喜びを課題の数だけ味わうことができるのです。
できない課題を登るためには、自分の弱さを認め、できない理由を深く考え、課題を観察し、甘い考えを自制する必要があります。
これはこの記事で説明してきた、内向的な人の能力に当てはまります。
要するに、できなかった課題を攻略し、自己成長の喜びを感じるためには、内向的な性格の強みが大変活躍します。
また、内向的なクライマーがトレーニングを行う場合、環境を整え、ストレスを減らす必要があります。
例えば「人が少ない時間帯や曜日を選択」「できるだけ少人数でのセッション」「信頼できる友人を作る」など、自分の能力が一番発揮できる環境づくりから始めましょう。
自分の強みを知り、環境が整えば内向型クライマーは誰もが目を見張る登りができるようになるでしょう。
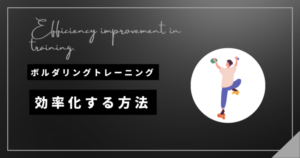
参考文献
https://core.ac.uk/download/pdf/144255161.pdf
https://psychclassics.yorku.ca/Jung/types.htm

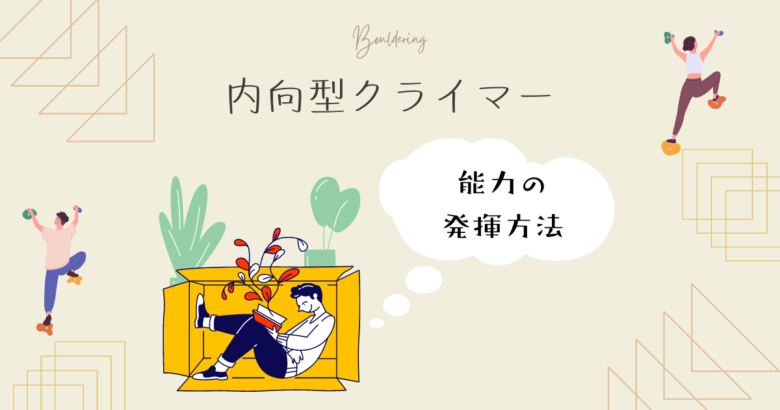




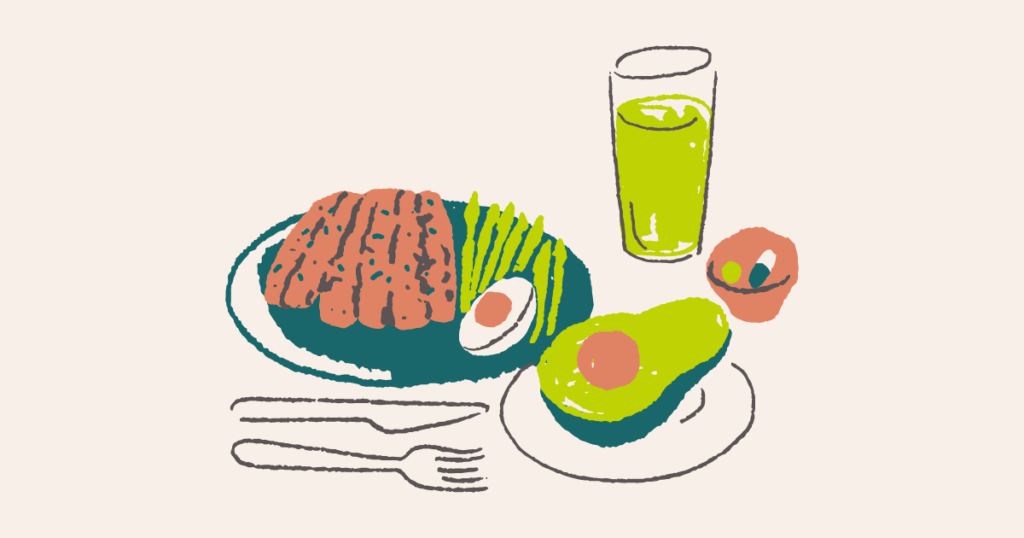





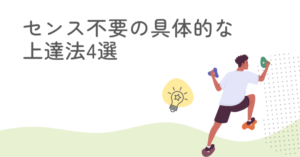
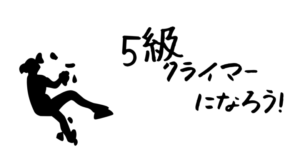

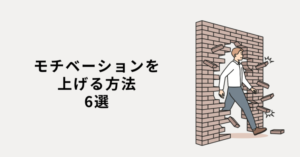


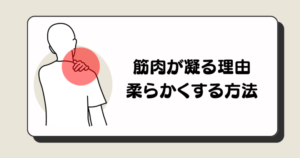
コメント