
「頑張ってるのに、うまくなってる気がしない」



「友達が先に上達していって焦る」



「自分の登り、何がダメなのか分からない」
……そんな気持ち、すごくよく分かります。
多くのボルダリング経験者が、ある時期に必ず感じる“成長停滞”の壁。
特に6~2級あたりを登っている方にとって、これは珍しいことではありません。
でも安心してください。
この伸び悩みは、センスや筋力不足のせいではありません。
今感じている焦りや不安も、必ず“成長のサイン”として受け止められるようになります。
この記事は5分ほどで読めます。
今、少しでも「壁を感じている」と思った方は、次の一歩を一緒に見つけていきましょう。
あなたの登りは、もっともっと成長できます。
多くの人が感じている「伸び悩み」の正体とは?
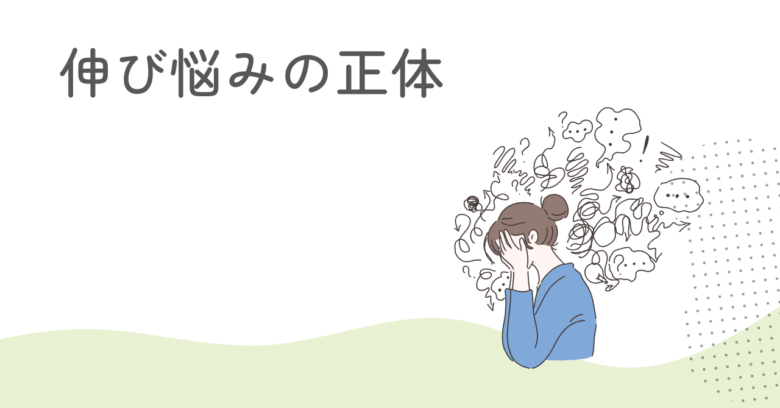
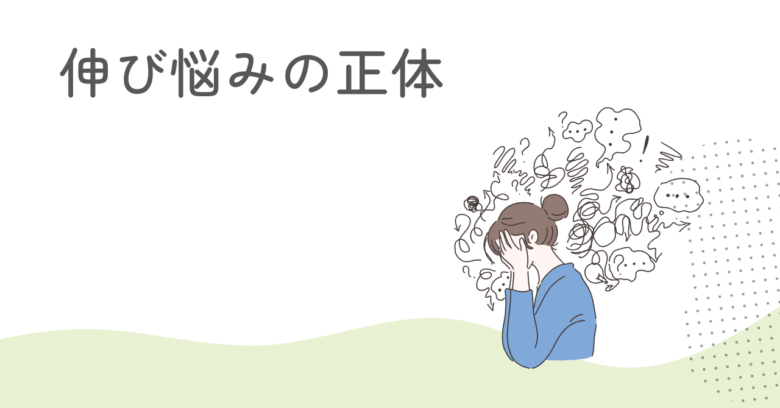
「週1〜2回はジムに通ってるのに、登れるグレードがずっと変わらない…」
「一緒に始めた友達が先に3級、2級を登れるようになってて、正直焦る」
「SNSでバシバシ課題を落としてる人を見ると、自分との差にモヤモヤする」
そんな風に感じている方はいませんか?それ、あなただけではありません。
ボルダリングを始めてしばらく経つと、多くの人が「最近、うまくなってる気がしない…」と感じるタイミングを迎えます。
実際、課題が登れなくなったり、前より自信を持てなかったりすると、成長が止まってしまったような不安に襲われがちです。
「自分にはセンスがないのかも」
「頑張ってるつもりなのに、なんで上達しないんだろう…」
そう悩む人の多くが、実は“努力の方向”をほんの少し間違えているだけ。
自分なりに頑張って登っているのに、なかなか成果を感じられないとしたら、登り方や練習方法に対して、どこかで「思い込み」をしている可能性があります。
次の章では、上達を妨げる4つのありがちな“間違った思い込み”を紹介します。
まずはその思い込みに気づくことが、「本当に伸びる練習」への第一歩です。
よくある“間違った思い込み”に注意しよう
ボルダリングの上達を妨げているのは、技術や筋力だけではありません。
多くの人が無意識に信じている“思い込み”が、成長のチャンスを奪っていることがあります。ここでは特に多い4つの誤解について解説します。
- ジムに通いさえすれば、自然と強くなる
- 難しい課題ばかりやった方が成長する
- センスがないと上達できない
- 登るにはより強い力が必要
■「ジムに通いさえすれば、自然と強くなる」


通うだけで強くなるなら、全員が短期間でグレードアップしているはずです。
しかし現実には、「何を意識して登るか」によって成長速度は大きく変わります。
たとえば、毎回なんとなく課題を選び、ゴールできたかどうかだけを気にしていませんか?
「このムーブはなぜ失敗したのか?」「次は何を変えるべきか?」と考えながら登ることで、成長のスピードは確実に上がります。
■「難しい課題ばかりやった方が成長する」


限界グレードに挑戦することは大切ですが、それがすべてではありません。
難しすぎる課題ばかりにトライすると、体勢が崩れたまま無理に登ろうとして、フォームが崩れてしまいます。
5級〜3級あたりを登っている方は、あえて1段階下の課題(例:6級や4級)で、「正確な重心移動」や「足の置き方」を見直す時間を作ることが効果的です。
上級者ほど“簡単な課題で丁寧な動き”を繰り返しています。
■「センスがないと上達できない」
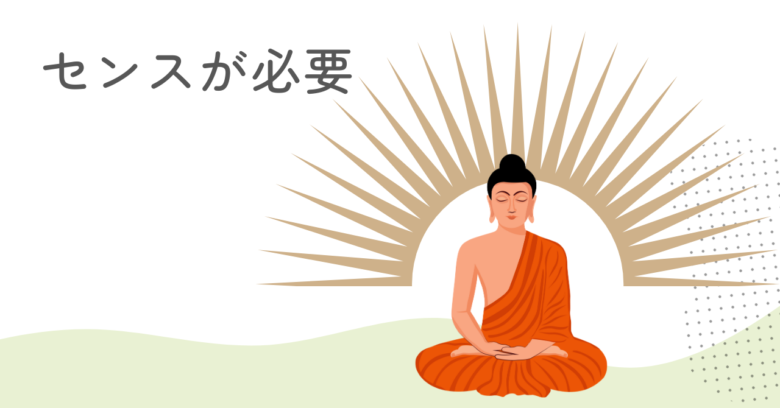
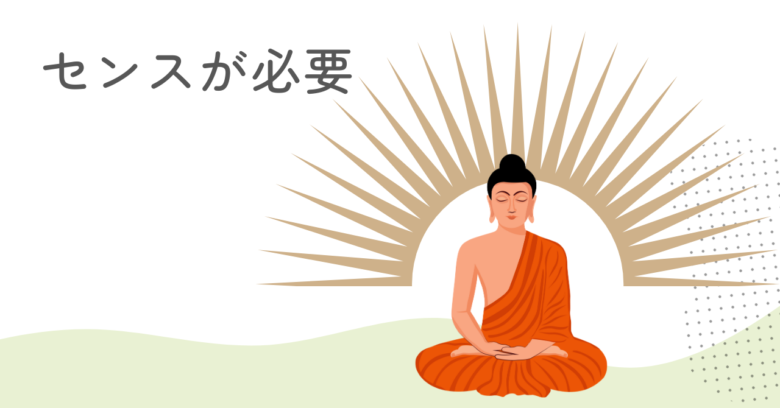
「自分には運動センスがないから…」と諦めていませんか?
確かに動きの理解が早い人もいますが、ボルダリングは“反復”と“思考”によって確実に上達するスポーツです。
実際、初めての頃は運動が苦手だった人でも、コツコツ振り返りを重ねることで上達した事例はたくさんあります。
センスよりも大事なのは、“自分の登りを分析して改善する力”です。
■「登るにはより強い力が必要」
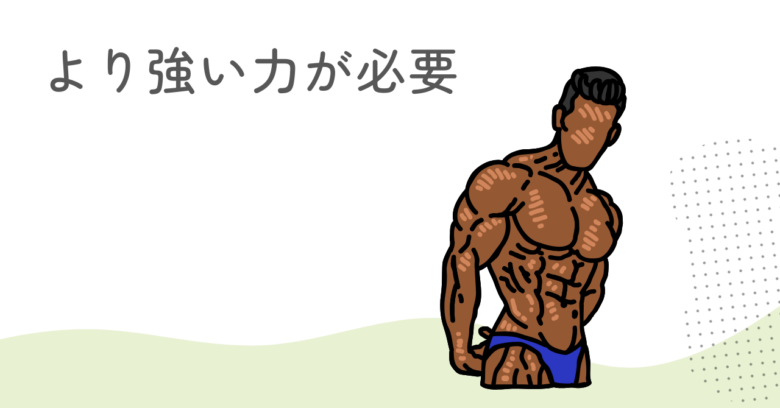
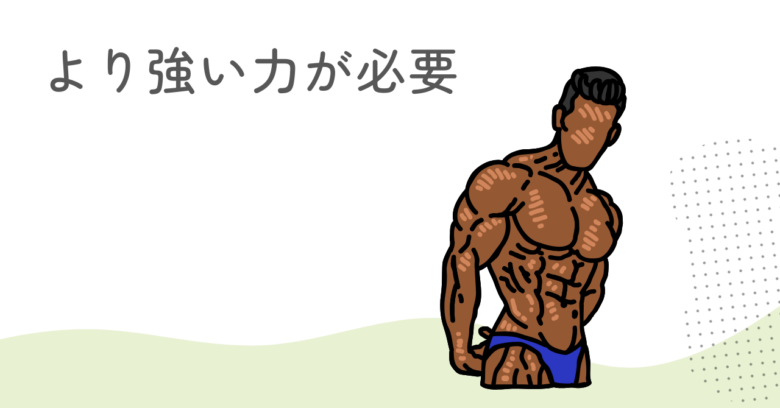
「この課題は腕の力が足りないから無理」と思った経験、ありませんか?
しかし、ボルダリングでは“力を使わないで登る”技術の方が重要です。
例えば、足にしっかり体重を乗せる「乗り込み」や、傾斜のある壁で「ねじる」体の使い方が上手くなると、腕の力をほとんど使わずに登れる場面が増えてきます。
筋力アップも必要ですが、それ以上に「楽に登るための身体の使い方」を覚えることが、グレードアップの近道になります。
\理論的に学びたい方にオススメ!/
ボルダリング上達法4選
「うまくなりたいけど、どう練習すればいいのか分からない…」
そんな方に向けて、センスや筋力に頼らなくても成果につながる、4つの実践的な上達法を紹介します。
どれもすぐに取り入れられる内容なので、次回のジムから試してみてください。
- 自分の登りを動画で「観察」する
- 完登よりも「試行回数の中身」を意識する
- 「ジム内の最も簡単な課題」でフォームを整える
- 上手な人と登る・真似する・話す
1. 自分の登りを動画で「観察」する


上達を目指すなら、自分の登りをスマホで撮影して“観察する”ことを習慣にしましょう。
他人の目線で自分を見ると、登っているときには気づけなかったクセやミスがよく見えるようになります。
例えば、「体が壁から離れてしまっている」「ホールドを掴む位置が浅い」「足を置き直すクセが多い」など、自覚のない課題が浮き彫りになります。
撮影は三脚がなくても、荷物棚やチョークバックに立てかけるだけで十分。
編集する必要もなく、見返すだけでOKです。
また、上手な人の動画を“研究”するのも効果的です。ただ真似るのではなく、「どこに重心があるか」「どのタイミングで次のホールドに出ているか」など、動きの“理由”を考えることがポイントです。
見る・考える・試すのサイクルを繰り返すことで、感覚だけに頼らない「再現性のある登り方」が身についていきます。
2. 完登よりも「試行回数の中身」を意識する


「登れた/登れなかった」だけで練習を終えてしまうのは、非常にもったいないことです。
上達したいなら、1トライごとに「何を試したのか?」「どう変えたのか?」を意識することが大切です。
たとえば、「1手目のバランスが崩れるから、スタートの足の位置を5cm外側にしてみる」など、小さな調整を重ねていくことが「試行」の質を高めます。
このとき、闇雲に回数をこなすのではなく、“仮説→実行→検証”という考え方を取り入れると一気に成長スピードが上がります。
ただ「がむしゃらにトライする」から、「毎回ちょっとずつ狙って変えていく」登り方にシフトすることで、完登しなくても確実に登りの質が上がっていきます。
研究では「目標設定とフィードバックを組み合わせてこそ技能向上効果が高い」と報告されているthesportjournal.org
3. 「ジム内の最も簡単な課題」でフォームを整える


「難しい課題を登れれば上達」と思いがちですが、実は簡単な課題こそフォーム修正に最適な教材です。
難易度が高い課題ではバランスが崩れたり、ムーブが雑になりやすく、自分の動きが正しいのかを見極めづらくなります。
正しいフォームは、クライミング中に無駄な力を使わず、効率よく登るための“土台”です。
フォームが崩れていると、力がうまく伝わらず、保持やバランスに無理がかかってしまいます。
たとえば、初心者の多くは腕の力で登ろうとしますが、正しいフォームでは足に重心を乗せるため、腕の疲労を抑えながら登ることができます。
そのフォームを整えるためには、7級や8級といった簡単な課題が最適です。
難しい課題ではバランスが崩れやすく、正しい動きを意識する余裕がありません。
特に重要なのは、骨盤と肩甲骨の位置。
骨盤が後傾すると体が壁から離れやすく、肩甲骨が丸まると動きが小さくなります。
骨盤を立てて胸を開き、肩甲骨を寄せることで、動きが安定し効率的になります。
自分のフォームを確認するには、登りを動画で撮って見返すのが効果的です。
モーターラーニングの観点からも、基礎動作を丁寧に繰り返し実行し、都度フィードバック(自己観察やコーチの指導)を得ることで動作が定着する。一方、上述の研究では「疲労耐性と動作経済性が登攀性能の主要因であり、単純な筋力練習だけでは十分な技術習得が得られない」とされているthesportjournal.org。
4. 上手な人と登る・真似する・話す
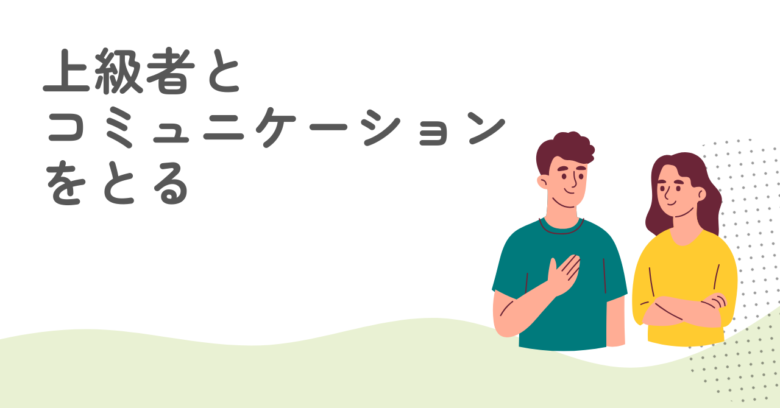
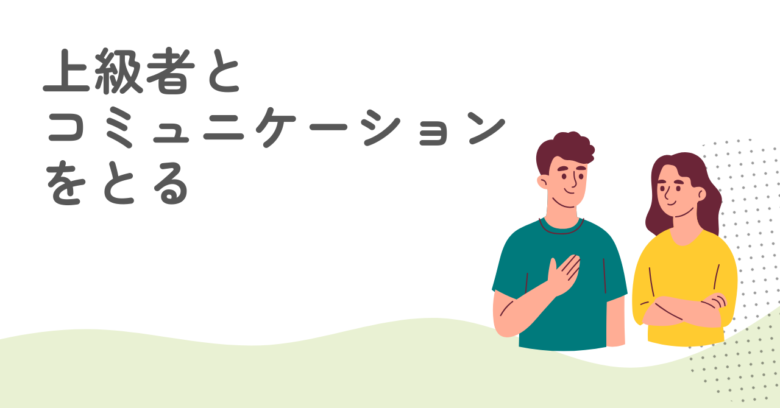
成長を加速させたいなら、自分より上手な人と登る機会を意識的に作ることがとても効果的です。
上級者の動きは、技術の宝庫。
彼らがどこを見て、どんな体勢で、どのタイミングで動いているのか?観察するだけでも多くの学びがあります。
特に意識したいのは、ムーブの“理由”を聞くこと。
「なんでその足を選んだんですか?」「ここで体を止めた理由は?」など質問してみると、自分にはなかった視点に気づかされます。
また、セッション中は他の人のトライを観察することも重要です。
「そのムーブは自分でもできる?」「違う方法があるとしたら?」と考えるだけで、自分の引き出しがどんどん増えていきます。
セッションは“ただ一緒に登る”場ではなく、知識と感覚の共有の場です。
自分の世界に閉じこもらず、人とのやり取りの中で得られる「気づき」が、あなたの登りを進化させてくれます。
必要な情報を言語化し、考えながら登る習慣が身につけば、自然と「上手い登り方」ができるようになります。
試行錯誤と観察学習の有効性: 一般的に、モーターラーニング理論では反復試行錯誤が技能上達に不可欠とされる。また、他者の動きを観察する**観察学習(モデリング)**も効果的である。系統的レビューでは、他者の動作を観ることで運動スキル習得が大きく促進される(観察学習未実施群よりも有意に上達した)と報告されているpmc.ncbi.nlm.nih.gov
系統的レビューでは、観察学習あり群はなし群に比べ運動スキル学習で明確に優れるとされるpmc.ncbi.nlm.nih.gov
\クライマーにとって買って損はない良書!/
センスが必要ないのはなぜか?
「どんどん上達していく人=センスがある人」と思われがちですが、実はそうとは限りません。
センスとは、直感的に動ける力、動きを再現する力、リズムの良さなどを指します。
たしかにそれらは一見“才能”のように見えますが、多くはその人の経験の積み重ねから育ったものです。
たとえば、スポーツ歴が長かったり、身体を使った遊びの経験が豊富だった人は、自然と感覚が磨かれていることが多いです。
つまり、「センスがある人」は、過去の経験を活かせている人なのです。
逆に言えば、今は上手くできなくても、繰り返し登って試行錯誤することで、センスは“育てていける”ということです。
「センスがない」と決めつけるのではなく、「まだ気づけていないだけ」と捉えて、自分の課題を振り返ったり、工夫を重ねていくことが大切です。
足りないのは才能ではなく、“学びと気づきのきっかけ”。
自分に何が足りないかを探しながら登り続けることで、感覚も技術も自然と磨かれていきます。
近年のスポーツ科学では、才能も後天的に鍛えられるものと捉えられている。体操選手研究では、運動学習能力(練習による上達度合い) を測ることが将来の成績予測に有効とされ、才能は練習・協調性で育つ指標とされたpmc.ncbi.nlm.nih.gov
タレント選抜の観点からも、能力の「現状」より「学習能力」が重視される。研究では、若い体操選手において協調性や技術習得能力が優れていた者ほど将来の成績が良かったとされ、才能は練習(運動学習能力)で伸ばせる指標と位置づけられているpmc.ncbi.nlm.nih.gov
「うまくならない」から抜け出すには、意識の向け方を変えよう
ボルダリングの上達に悩んでいる人の多くは、「頑張っているのに成果を感じられない」という不安を抱えています。
でもそれは、努力が足りないからではなく、努力の方向が少しだけずれていることが原因かもしれません。
第3章で紹介したように、「ジムに通ってさえいれば強くなる」「難しい課題ばかりやれば成長する」などの思い込みは、実は成長を妨げる落とし穴。
そこから抜け出すには、自分の登りを客観的に見直し、小さな改善を重ねることが大切です。
第4章でお伝えした上達法は、センスや特別な才能がなくても実践できるものばかり。
そして第5章では、「センスがない」と思っていた人でも、視点と取り組み方次第で感覚を育てていけることをお伝えしました。
大事なのは、「自分には才能がない」とあきらめることではなく、「どうすればもっとよくなるか?」と問い続けることです。
気づき、改善し、また試す。その積み重ねが、あなたの登りを確実に変えてくれます。
うまくならない焦りを、うまくなるヒントに変えることで、ボルダリングはもっと楽しく、充実したものになっていきます。
\意外と楽しい!世界で流行りのボルダーボール!/

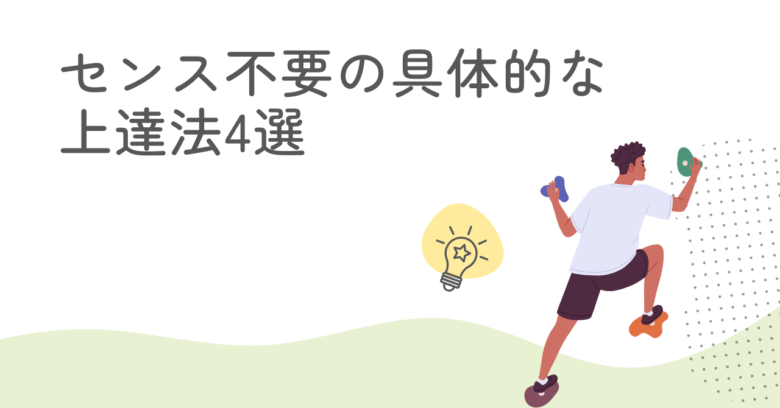




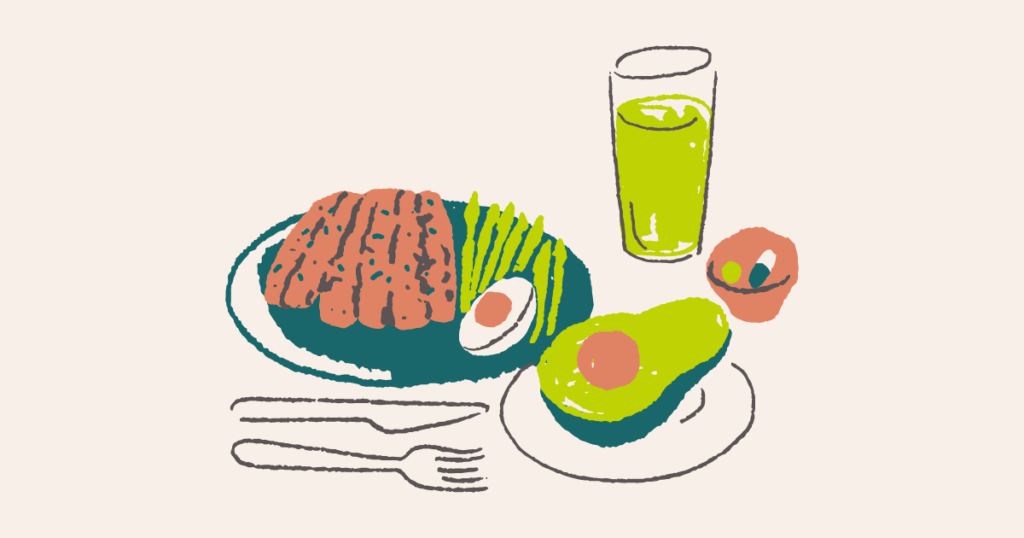





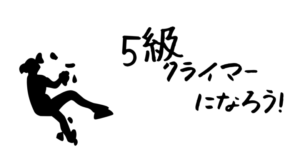

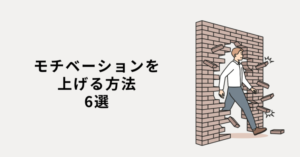



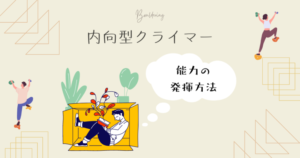
コメント