ボルダリングジムの顔。
と言ってもいいのはやはり、課題の質です。
その、課題の質を大きく左右するものは、ホールドのつけ方。
ボルダリングジムのホールドのつけ方には種類があります。
知っていましたか?
ホールドのつき方には大きく分けて2種類あります。
「ラインセット」
と
「まぶしセット」
です。
この二種類のセット方法にはどのような違いがあるのでしょうか。
メリットとデメリットを詳しく説明していきたいと思います。
この記事を書いた人
ぶちょー(クライミング飛鳥店長)
15歳からクライミングをはじめ、現在30歳。
趣味は読書やカメラ。
【登ってきた主な課題】
最高RP 四段+(V13) 5.13d
ハイドラ(四段+) フルチャージ(四段) Ammagamma (V13)Midnight Lightning(V8)などなど
リキッドフィンガー 5.13d

\本を読んで基本をおさらいしましょう!/
ラインセット
【諏訪店】今週末のマンスリーSETでは黄色、赤色課題が無くなります❗️
— Edge and Sofa BoulderingPark (@EdgeandSofa) April 2, 2019
あの課題達も4/4(木)までです‼️
怒涛のチャレンジお待ちしております🙌#エッジアンドソファー #クライミング #ボルダリング #ラインセット pic.twitter.com/gbO7uBlQgw
ラインセットというのは一般的に、設定されている課題の分のみ、ホールドがついている壁を指します。
コンペ壁ともいったりしますね。
課題を作りながらホールドを付けていくセット方法で、基本は課題ごとに色やホールドの種類が統一されています。
ホールド替えまでの期間が短いのも特徴です。
ラインセットのメリット
- 大きなホールドが付けやすい
- インスタ映えする
- 課題が分かりやすい
- オブザベがしやすい
- 他のホールドが干渉しにくく登りやすい
- コーディネーションが多い
ラインセットとは、壁の上に設置されたホールドをルートごとに整理し、決められた色やテープでルートを明確に区切った課題のことを指します。
ホールドの間隔や配置にゆとりがあるため、他の課題のホールドが干渉しにくく、登りやすいのが大きなメリットです。
特に「オブザベーション(登る前にルートを目で読み取ること)」がしやすく、どこを使えばいいのか一目で分かるため、初心者でも迷わずトライできます。
また、大きなホールドを多用できることから、見た目が華やかで「インスタ映え」しやすく、映像や写真にも映えます。
さらに、ジャンプや体の振りなどのダイナミックな動き=「コーディネーション系ムーブ」も設定しやすく、競技志向のトレーニングにも適しています。
登る課題が視覚的に明快なので、ボルダリング初心者の導入にも最適です。
ラインセットのデメリット
- 課題数が少なく飽きやすい
- 長モノができない
- 自分で課題を作ることができない
- セッションがしにくい
- 小さなホールドが少ない
- 壁が傷みやすい
ラインセットは視認性や登りやすさに優れている一方で、いくつかのデメリットもあります。
まず、設定された課題(登るルート)の数が限られており、頻繁に更新されないジムでは「飽きやすい」と感じることがあります。
また、壁のスペースを多く使うため、スタートからゴールまでを長く設定する「長モノ(ロングルート)」の課題が作りづらく、持久力トレーニングには向きません。
さらに、課題があらかじめ決められているため、登る人自身が自由に課題を作ることはできず、「今日はこの動きを練習したい」といったニーズには対応しにくい側面もあります。
セッション(複数人で同じ課題に挑戦する遊び)も、ルールが固定されていることで自由度が下がる傾向にあります。
また、使われるホールドは大きめのものが多く、指先の細かい保持力や繊細な足置きを鍛えるために必要な「小さなホールド」はあまり使用されません。
そして、ホールドの取り付け・取り外しが多く行われるラインセットの壁は、ビス穴の消耗が早く、壁材が傷みやすいという運営上の課題もあります。
まぶしセット

まぶしセットとはその名の通り”ホールドがまぶされている壁”のことを指します。
まぶし壁、トレーニング壁ともいいますね。
もともとセットされている課題分以外のホールドもついています。
ホールドを付けてから課題を作るセット方法で、色やホールドの種類はバラバラです。
ホールド替えの期間は長く、ある程度は課題が残っているのが特徴です。
なお、まぶしセットで、テープを貼る隙間もなくすくらい超高密度にホールドを詰め込むと「パズルセット」といったりもします。
このパズルセットはホールドを探したり覚えたりするのに、慣れるまで時間がかかりますが、慣れてしまえば強くなれる壁としてとんでもない効果を発揮します。
まぶしセットのメリット
- 課題が無限に作れる
- 長モノができる
- 課題が作りやすい
- 飽きにくい
- セッションしやすい
- 小さなホールドに強くなる傾向
- 壁が傷みにくい
まぶしセットとは、壁に非常に多くのホールド(手や足をかける突起)を隙間なく設置したボルダリングの壁です。
このタイプの壁では、ホールドの組み合わせが無限に近いため、自分で自由に課題(登るルート)を作成できます。
特に「岩場の課題の再現」や「特定ムーブの反復練習」に最適です。
また、ルートの距離を長く設定しやすいことから、「長モノ(ロングルート)」にも対応でき、スタミナやリズムを鍛える練習にも有効です。
登る人がその場でホールドを指定し合うことで簡単に新しい課題を作れるため、セッションもしやすく、コミュニケーションも自然に生まれます。
ホールドの種類や大きさが多様なので、指先の力や繊細な足置きが必要になり、小さなホールドに強くなれる傾向も。
また、課題を追加してもホールドを外すことが少ないため、ビス穴が劣化しにくく、壁自体が傷みにくいという運営面でのメリットもあります。
自分のレベルや目的に合わせて、自由度の高い練習ができるのが最大の魅力です。
まぶしセットのデメリット
- 課題が分かりにくい
- オブザべしにくい
- 他のホールドが干渉しやすい
- コーディネーション課題があまりない
- 映えにくい
まぶしセットは自由度が高い一方で、いくつかの注意点もあります。
まず、ホールドが密集しているため、課題のルートが明確に分かりにくく、「どこを使って登るのか」が初心者には特に見えにくい傾向があります。
これは「オブザベーション(登る前に課題を目で読み取る作業)」の難しさにもつながり、特に初級者にとっては登る前の不安要素になりやすいです。
また、ホールドが密集しているがゆえに、隣り合うホールドが手や足に干渉しやすく、想定外の使い方をしてしまうことも。
加えて、まぶし壁は「コーディネーション課題(ジャンプや体を大きく振ってタイミングよくホールドをつかむ動き)」のようなダイナミックなルートを設定しにくいため、スピード系や映像映えする動きの練習にはやや不向きです。
さらに、見た目はどうしてもホールドが密集してゴチャゴチャして見えるため、写真やSNS映えにはあまり向かないという点もあります。
総じて、自由度と引き換えに視認性やビジュアル性はやや下がるというのが、まぶし壁の弱点と言えるでしょう。

結局、強くなるのはどっち!?
まぶしセットとラインセット。
結局のところ、どちらが強くなれるのでしょうか…
個人的な意見になりますが、僕はまぶし壁の方が強くなれると思います。
なぜなら僕は、「自分で課題を作れる」ことと、「課題がある程度残ること」、そして「セッションがしやすいこと」にメリットを感じているからです。
岩の課題を目標にしている人にとっては、自分で課題を作ることにより、自分にとっての弱点が鍛えやすいですし、ある程度の期間は課題が残るため、長期目標のためのトレーニングには最適です。
まぶし壁は、保持力や足を丁寧に置く技術なども鍛えやすい壁ですね。
セッションに混じりやすいというメリットは具体的に、強い人と一緒に登ることにより、自分に足りないものや長所が明確になります。
とは言っても、ラインセットでは鍛えられないのか、というとそういうことでもなく、ラインセットにはラインセットの良さがあります。
大きなホールドやハリボテを使って立体的な動き、コーディネーションなどの運動神経トレーニングに向いています。
ラインセットでトレーニングをすると、体幹などのボディが強くなる傾向にあります。
コンペを目標にしている方は、ラインセットのほうがトレーニングになるでしょう。
また、課題の見栄えの面では圧倒的にラインセットの方が映えます。
前述のメリット、デメリットで説明している通り、まぶしセットのメリットはラインセットのデメリットとなり、その逆も然りです。
どちらのセットにもいいところがあり、悪いところがあるのです。
また、好みの問題もあります。
みんなでワイワイセッションがしたいならまぶし壁で登ると良いですし、コンペのような課題が楽しみたいならラインセットで登ると良いでしょう。
これらのことから、まぶしセットの壁、ラインセットの壁、お互いの長所を意識してどちらも登ったほうがより強くなれる。
と、いうのがこの記事の結論です。
ちなみに僕は9割5分まぶし壁で育ちました。
コンペは苦手です。^^;
\意外と楽しい!世界で流行りのボルダーボール!/

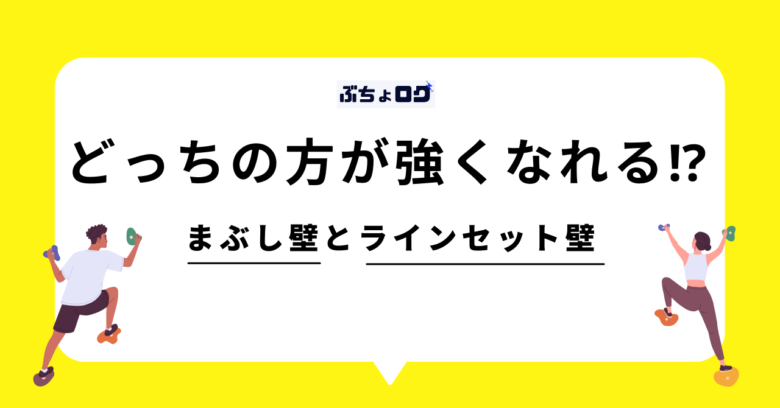



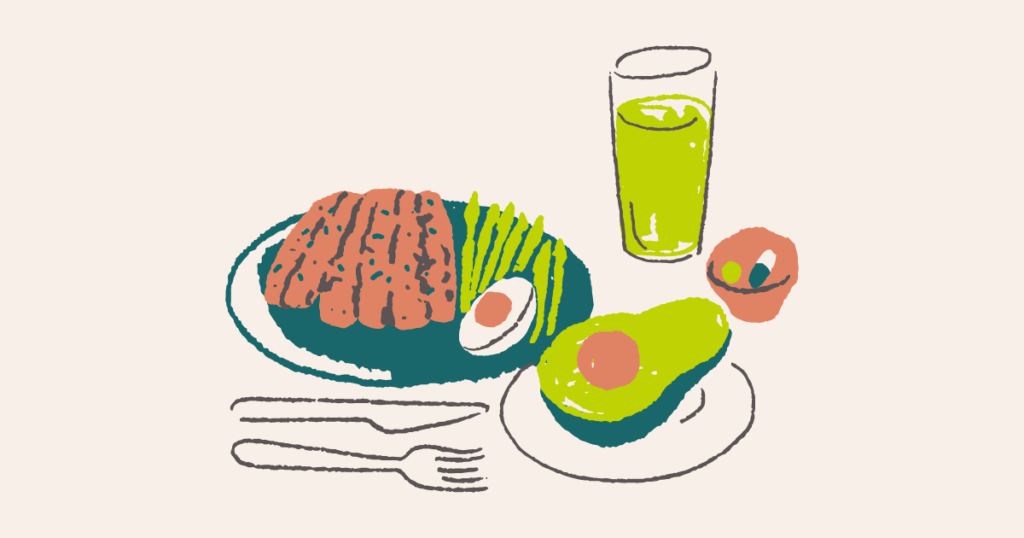





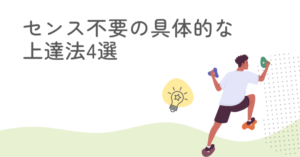
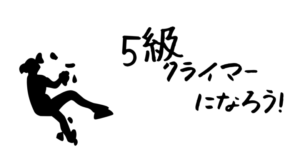
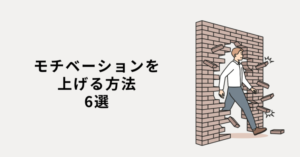



コメント